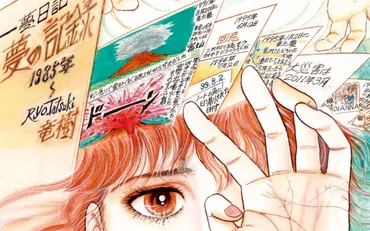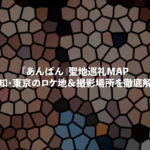1. 香港SNSでバズった“漫画の予言”とは
「2025年7月に日本で巨大地震が起きる」――そんなショッキングな噂がネットを中心に日本国内外で拡散しています。この情報の“震源地”となったのは、実は香港のSNSコミュニティでした。
“漫画の予言”はどのようにして広まったのか?
2025年春、香港や台湾のSNSや掲示板である日本の人気漫画が話題に。「2025年7月、日本に大地震」と読める描写があり、これを“予言”だと解釈したユーザーによる投稿がバズりました。
中国語圏のSNSでは「日本旅行は7月に行かない方がいい」「あの漫画家は過去にも未来を当てている」など、憶測が加速。さらに日本国内の翻訳系アカウントや、まとめサイト、YouTubeチャンネルによって紹介され、日本人ユーザーの間でも話題に。
デマが拡散するメカニズム
SNS上では、インパクトの強い話題ほどアルゴリズムによって拡散されやすい傾向があります。
とくに「有名人の発言」「漫画や映画のシーン」「不安をあおる内容」には、バズを狙うユーザーやまとめサイトが便乗しやすく、気付けば“既成事実”のように扱われてしまうことも。
本来はフィクションである漫画のワンシーンも、「現実の地震予知」として拡大解釈され、デマが独り歩きする結果となりました。
2. 公式見解:気象庁は「日付を指定した地震予知は不可能」と明言
こうした「○月×日に地震が起きる」といった話題が出るたび、日本の気象庁は公式に否定を続けています。
2025年6月にも、公式サイトや記者会見にて「現代の科学では地震の発生時期や場所を正確に予知することはできません」と明確にアナウンスされています。
予知と予測の違い
「地震予知」は、特定の日時・場所・規模までピンポイントに予告することを指します。しかし現在の地震学では、プレートの動きや過去の履歴から「この地域は今後30年で〇%の確率で大地震が起きる」といった**長期的なリスク評価(地震予測)**はできても、具体的な日時まではわかりません。
科学的根拠はなし
有名な「東海地震」や「南海トラフ地震」も、発生確率やリスクは示されていますが、「いつ発生するか」までは誰にも予測できません。過去には1995年の阪神・淡路大震災や、2011年の東日本大震災も、前兆現象や“予言”で正確に当たった事例はひとつもありません。
3. 旅行キャンセル続出――実害が起きる理由
根拠のない“地震予言”が流布された結果、実際に日本への旅行や出張を控える人が増えています。
とくに香港、台湾、中国本土の観光客から「キャンセル相次ぐ」「飛行機やホテルの予約が減少」といったニュースも報じられています。
経済への影響
観光庁のデータによれば、2023年の訪日外国人旅行者は約2,500万人。そのうちアジア圏の観光客が半数を占めます。今回のような“風評被害”で数パーセントでもキャンセルが生じれば、数十億円単位の経済損失となります。
体験談や口コミでさらに拡散
「日本旅行のキャンセル料を払った」「家族に止められた」など、リアルな体験談がSNSや掲示板に投稿されると、「やはり危ないのでは?」という心理的な連鎖が起こりやすくなります。こうした“口コミ効果”は一度火がつくと止まりません。
4. なぜ人は“予言”を信じるのか:心理とアルゴリズム
人間の不安心理が背景に
地震や災害のように「いつ起きるかわからないリスク」は、人間に強い不安をもたらします。この“不確実性への恐怖”が、つい「誰かの予言」や「話題の漫画」にすがりたくなる心理につながります。
- バーナム効果:「誰にでも当てはまる内容」を“自分だけの運命”だと信じてしまう心理。
- 確証バイアス:自分の不安や先入観に合う情報だけを信じてしまう傾向。
- 情報の過剰接触:SNSのタイムラインや動画サイトの“おすすめ”機能が、同じ内容のデマや噂を繰り返し目にする原因に。
SNSアルゴリズムの影響
YouTubeやX(旧Twitter)などのSNSは、「閲覧数」や「エンゲージメント」を最大化するために、バズりやすいショッキングな話題を目立つ場所に表示します。そのため「地震の予言」「予知夢」などのコンテンツが拡散されやすく、興味がなかった人にも情報が“押し付けられる”構造です。
5. 今日からできる防災ハック5選
デマに惑わされるよりも、日々の備えが何より重要。
“やってみたくなる”簡単防災ハックを5つ、実践方法付きでご紹介します。
5-1. 食料・水の“ローリングストック7日分”
- 水は1人1日3リットル×7日分=21リットル。2リットルのペットボトルを10本以上用意。
- レトルトご飯、缶詰、カップ麺、パウチのおかずなど、普段から食べるものを多めに買い置き。
- 賞味期限が近い順に使い、減った分だけ買い足す「ローリングストック」方式ならムダがない。
5-2. モバイルバッテリーを常にフル充電
実践ポイント
- スマホのバッテリー切れ=情報源喪失。
- 1台だけでなく家族分も用意。容量10,000mAh以上ならスマホ2~3回分充電可能。
- 停電時のため、ソーラーパネル付きや手回し発電機能付きの充電器も検討を。
5-3. 靴は“枕元”に
実践ポイント
- 夜中の地震ではガラス片や家具の破片で床が危険に。
- スニーカーや上履き、かかとのあるサンダルを枕元やベッドサイドに置く習慣を。
- 軍手や厚手の靴下もセットで用意すると安心。
5-4. 家族との連絡方法を確認
実践ポイント
- 災害時は携帯電話がつながりにくくなる。
- **災害用伝言ダイヤル「171」**や、NTTの「災害用伝言板」を事前に家族全員で使い方確認。
- LINEやSNSグループでも「安否確認専用トーク」を作り、いざという時の決まりごとを決めておく。
5-5. 「避難場所」と「危険エリア」を地図でチェック
実践ポイント
- 各自治体のホームページやアプリで「防災マップ」をダウンロード。
- 近所の避難所・危険エリア(河川、崖、古い建物など)を家族で実際に歩いて確認。
- 2ルート以上の避難経路を考え、夜や雨の日にも歩いてみる。
6. フェイクニュースに惑わされないチェックリスト
最後に、日常で使えるフェイクニュース対策のセルフチェックリストを紹介します。
- 情報源の信頼性
→ 発信元は政府・自治体・専門家か?出典が不明な場合は疑う。 - 一次情報の有無
→ 公式発表、学術論文、専門家のコメントを直接確認。伝聞・引用ばかりの情報は要注意。 - 極端な表現や感情をあおる内容に注意
→ 「絶対」「必ず」「100%」といった断定や、不安や怒りを強調する記事は疑ってみる。 - 複数の情報を比較する
→ 1つのニュースだけでなく、複数のメディア・公式サイトを確認する。 - 拡散の前に5秒考える
→ 急いで「シェア」や「リツイート」する前に、一呼吸置いて本当に信じていいか冷静に考える。 - AI生成や加工画像にも注意
→ 最近はフェイク画像・動画も簡単に作られます。不自然な部分がないかチェック。
まとめ
2025年7月「日本で巨大地震が起こる」という噂は、科学的根拠がないSNS発のデマであり、公式機関も否定しています。
しかし、日本は世界有数の地震大国。「デマだから大丈夫」ではなく、日々の備えや正しい情報収集こそが“本当の安心”につながります。
噂に振り回されず、「自分と家族を守る力」をアップデートして、災害にも強い毎日を送りましょう。
こちらもおすすめ