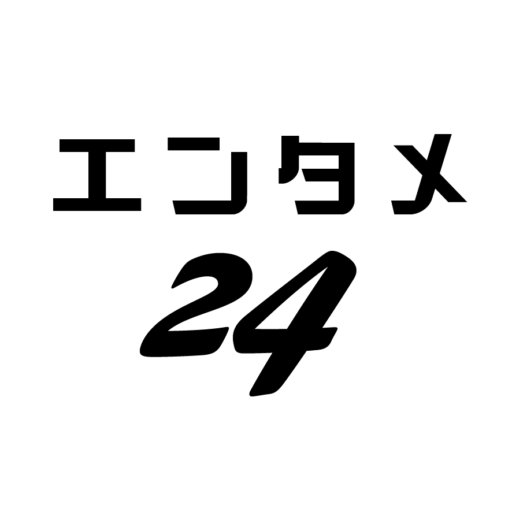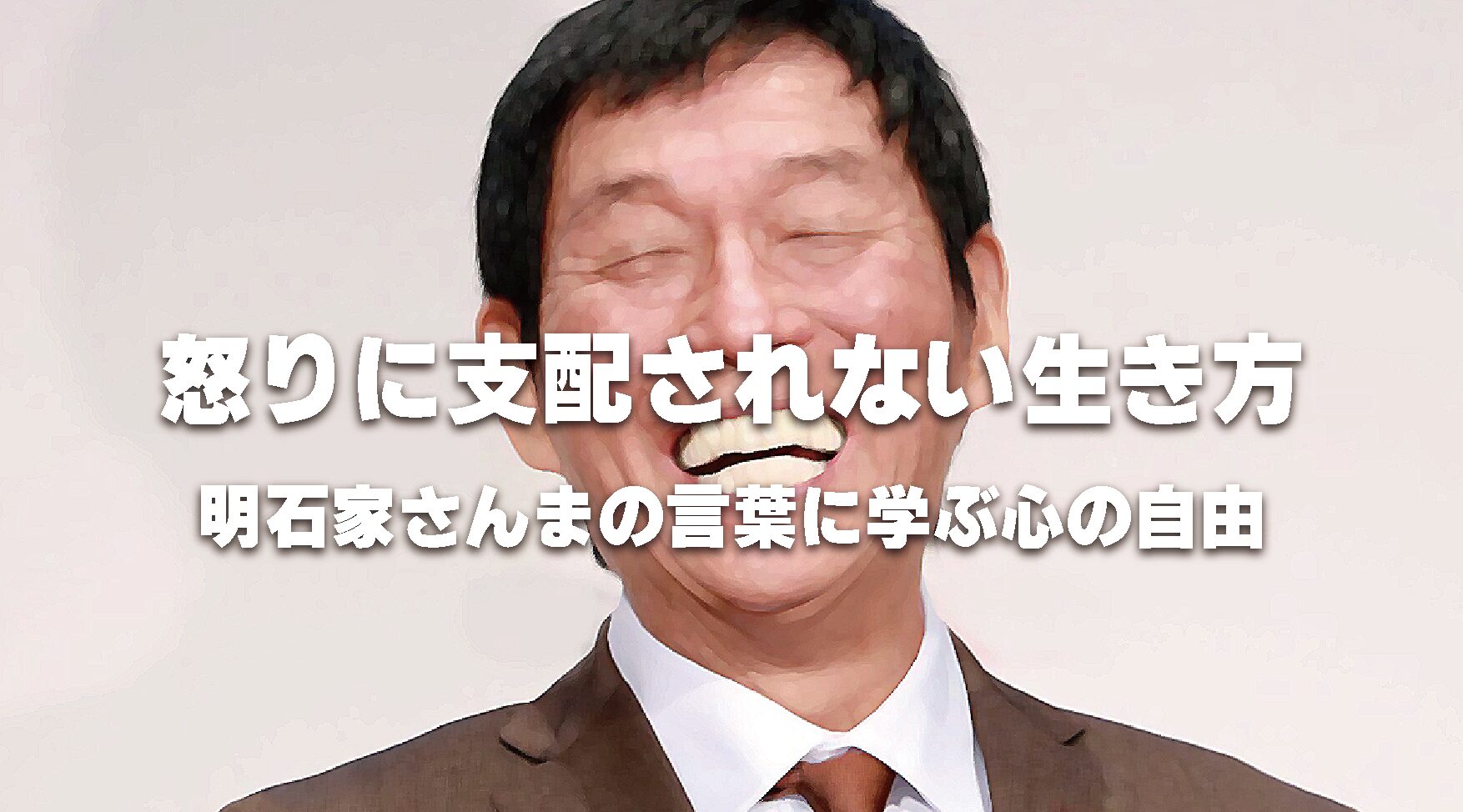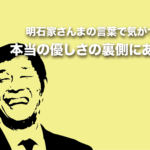怒りに支配されない生き方
怒りの連鎖から抜け出せない日々
「なんでこんなにイライラしてしまうんだろう?」
自分の小さなミスや他人の言動に腹を立ててばかりの日々。電車で押し合う人、会議で自分の意見を否定される瞬間、SNSでの心ないコメント。怒りは生活のどこにでも転がっている。
ある日、そんな自分が恥ずかしくなるきっかけが訪れた。バラエティ番組で明石家さんまさんが放った何気ない言葉が、心にズシンと響いたのだ。
「腹が立つことがない、まず人に対して嫉妬心がない、自分に対して過信もしていない」
これを聞いたとき、笑いを交えた軽い調子とは裏腹に、何か大事な真理に触れたような気がした。

生まれた時から、ずっと面白い!
「国民的芸人」の偉大な足跡をたどる、本邦初の「明石家さんまヒストリー」。
人生を「明石家さんま研究」に捧げた男による、渾身のデビュー作!
誕生から少年時代、落語界への入門、大阪での活躍、「オレたちひょうきん族」スタートまで、明石家さんまの「1955~1981」を克明に記した第1巻。
師匠のもとで芸を磨き、芸人仲間と切磋琢磨しながら順調にスターの階段をのぼる一方で、芸を捨てる覚悟をした大恋愛、ブレイク前夜の挫折など、苦くも充実した“青春時代"を、本人の証言と膨大な資料を駆使して浮かび上がらせます
「腹立つ」という感情のメカニズム
怒りとは何だろうか?心理学的に見ると、怒りは「自分の価値観や期待が他者によって侵害されたと感じたとき」に生まれる感情だという。この説明を聞いて、ふと思い返した。自分がイラっとするのは、結局「こうであるべき」という勝手な思い込みが壊れたときなのだ。
- 上司が自分の提案を採用しなかった
- 電車の中でマナーの悪い人に遭遇した
- 友人が約束を破った
どれも、自分の価値観が「正しい」と信じているからこそ怒りが湧いてくる。これがさんまさんの言葉で言うところの「過信」だ。「自分の価値観こそが正しい」と無意識に信じてしまっている自分がいる。
「なんやねんコイツ」と思う人への対処法
さんまさんはさらに続ける。
「『なんやねんコイツ』と思うことはあるけど『コイツアホやねんな』と思う」
これが実に妙だ。怒りを抱く代わりに「ああ、アホなんだな」と思うだけにする。アホという言葉が、怒りの炎を消す魔法の言葉に思えてきた。
日常の中で、この考え方を試してみた。たとえば、会議中に割り込んでくる人がいても「この人、話すタイミングがわからないだけか」と考える。すると、驚くほど気持ちが軽くなる。そう考えるだけで、自分がその状況に引きずられなくなるのだ。
「腹を立てる器じゃない」という発想
さんまさんの名言の核心はここにある。
「腹を立てられる器でもない、そんなに偉くない」
この言葉には、深い謙虚さが詰まっている。「自分は立派で、他人を裁ける立場にある」と思っているから怒りが生まれる。では、そうでないとしたら?自分は完璧ではないし、他人もまた完璧ではない。みんな不完全な人間同士なのだから、怒りで裁こうとすること自体がナンセンスだ。
嫉妬心がない人の強さ
さんまさんの「嫉妬心がない」という姿勢も、怒りを軽減する大きな要素だ。他人が成功したとき、「羨ましい」と思う気持ちは自然な感情だが、それが「なんで自分じゃないんだ!」という怒りに変わるとつらい。さんまさんのように「他人の成功をただの出来事として捉える」心の余裕があれば、嫉妬心も薄れていく。
怒りを捨てた先にあるもの
怒りを手放すと、何が変わるのだろうか?まず、心が軽くなる。そして、他人に振り回されず、自分の時間を大切にできるようになる。怒りにエネルギーを費やす代わりに、その分を笑いに変えたり、創造的な活動に使ったりするほうが、よっぽど自分のためになる。
終わりに:明石家さんまの言葉を日常に生かす
明石家さんまさんの言葉には、大きな教訓がある。それは「怒りから自由になる」ということ。怒りを抱えたままでは、自分自身を縛ることになる。だからこそ、「アホやねんな」と思う余裕を持つ。「自分はそんなに偉くない」という謙虚さを持つ。それが、心を軽くして生きやすくするコツなのだ。
次にイラっとしたとき、こう考えてみてほしい。「腹を立てたところで、この人が変わるわけでも、自分が偉くなるわけでもない」。その瞬間、自分の中に自由が生まれる。そしてその自由こそが、生きやすさを手に入れるカギなのだ。
こちらもおすすめ
あとがき
笑いを交えながらも、深い洞察を与えてくれるさんまさんの言葉。その一つ一つが、日々の生き方を見直すきっかけになる。このエッセイが、少しでも誰かの心に響き、怒りの連鎖から解放される助けになれば幸いだ。