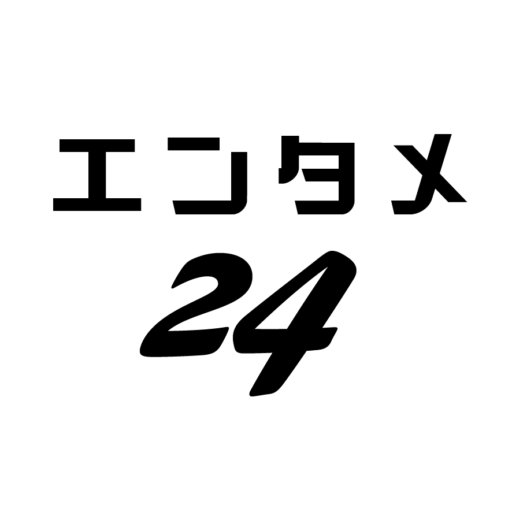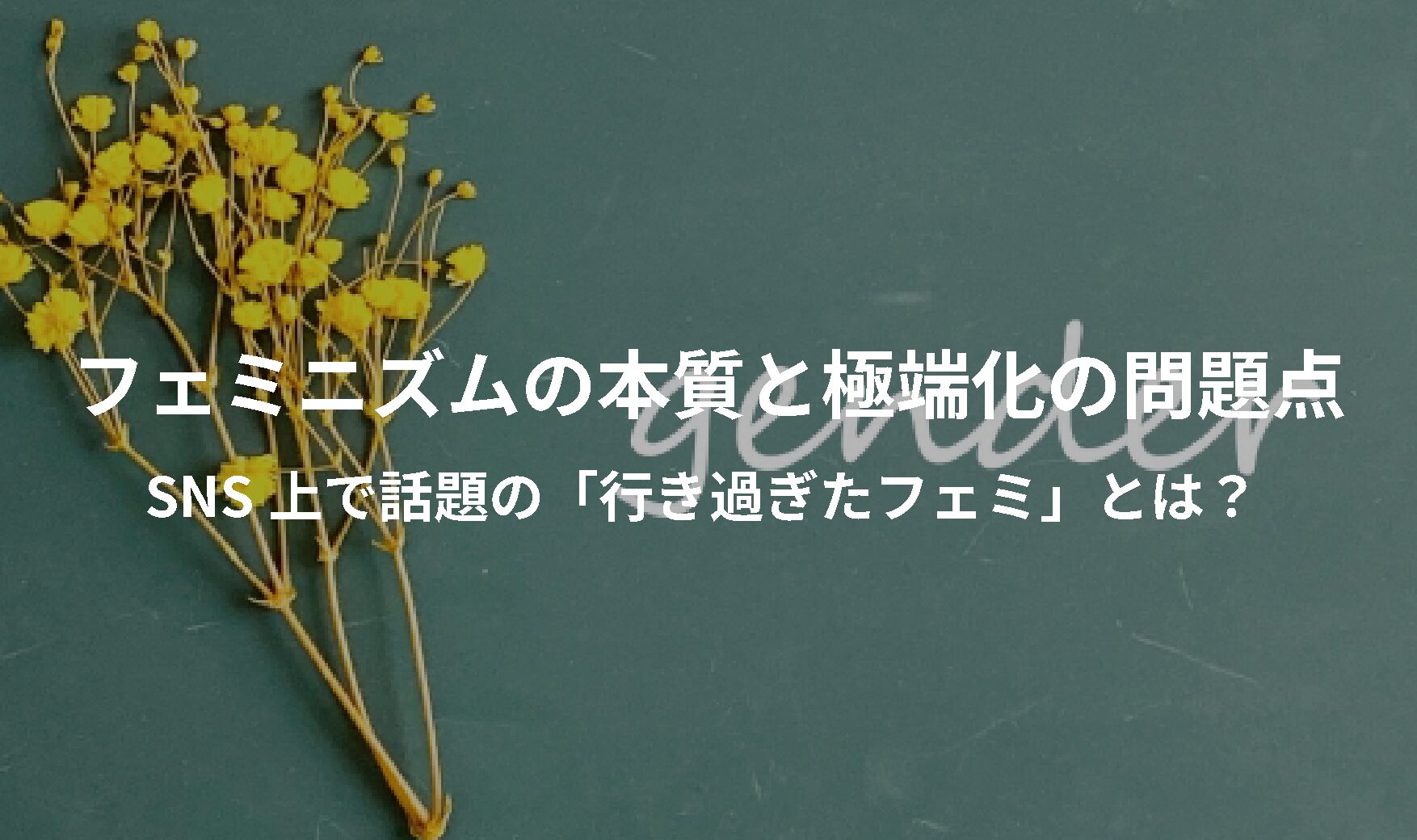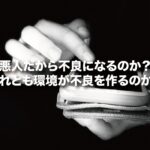SNS上で話題の「行き過ぎたフェミ」とは?
はじめに
フェミニズム(Feminism)とは、男女平等を目指し、女性の権利向上を推進する思想や運動のことを指します。本来、すべての人が性別によって不当な差別を受けない社会を目指すものですが、一部では過激な主張や行動が目立ち、批判を受けることがあります。特に近年は、SNSなどで過激なフェミニスト(通称「ツイフェミ」など)が発信する内容が物議を醸すことも少なくありません。
本記事では、「行き過ぎたフェミ」と呼ばれる現象について、その特徴や問題点を考察しつつ、本来のフェミニズムの意義を再確認していきます。また、フェミニズム運動の歴史やエビデンスを交えながら、より良い男女平等のあり方についても考えていきます。

フランス革命以降、人権への強い関心の潮流は止まらず、世界は今最もリベラル化していると言える。とはいえ、さらに男性に変化が求められる近年は、フェミニズムの視点抜きで、国や企業の成長は語れない。世界標準に遅れ、その分、伸びシロたっぷりの日本が知るべき「男女同権」の歴史とは? 米国で家族法を学び、自身も後発で目覚めた著者が、熱狂と変革のフェミニズム史を大解剖。ウルストンクラフト、ボーヴォワール、マッキノン、与謝野晶子など、主要フェミニスト五十余人を軸に、思想の誕生とその展開を鷲掴みした画期的な入門書。
フェミニズムの本来の目的とは?
まずは、フェミニズムの基本的な概念と、その歴史を振り返ってみましょう。
フェミニズムの歴史
フェミニズムには大きく分けて「第一波」「第二波」「第三波」「第四波」の流れがあります。
- 第一波フェミニズム(19世紀~20世紀初頭)
- 主要な課題は、女性の参政権(選挙権)の獲得。
- アメリカやイギリスで女性参政権運動が活発化。
- 1920年、アメリカで女性参政権が認められる。
- 第二波フェミニズム(1960年代~1980年代)
- 女性の社会的・経済的な権利拡大が焦点。
- 男女の賃金格差、性別による役割分担の問題に取り組む。
- 日本では1970年代に「ウーマン・リブ」運動が盛んになる。
- 第三波フェミニズム(1990年代~2000年代)
- 個人のアイデンティティの尊重、多様性の受容を重視。
- LGBTQ+の権利問題とも連携。
- 第四波フェミニズム(2010年代~現在)
- SNSの普及により、オンラインでの活動が活発化。
- 「#MeToo」運動など、性暴力の告発が増加。
このように、フェミニズムは時代ごとに変化しながら進化してきました。しかし、SNSの発展により、「行き過ぎたフェミ」とも言われる極端なフェミニズムの動きも目立つようになっています。
「行き過ぎたフェミ」とは? その特徴と問題点
「行き過ぎたフェミ」とは、本来のフェミニズムの目的である「男女平等」から逸脱し、男性への攻撃的な言動や、過激な主張を伴うフェミニズムを指すことが多いです。具体的にどのような特徴があるのか、見ていきましょう。
1. 男性嫌悪(ミサンドリー)の傾向
一部の過激なフェミニストの中には、「男性そのものが悪である」とする主張をする人もいます。これは、男女平等の理念とは根本的に異なる考え方であり、逆差別を生む危険性をはらんでいます。
例
- 「男性は全員加害者予備軍」といった過激な発言
- 男性がフェミニズムを支持しても「男だから信用できない」と排除する姿勢
参考
研究によると、極端なミサンドリー的思考を持つ人々は、社会的な疎外感や過去のトラウマが背景にあることが多いとされています。(出典:Tellings Asahi)
2. 建設的な議論よりも攻撃的な言動
フェミニズムは本来、男女ともに対話を通じてより良い社会を築くことを目的としています。しかし、行き過ぎたフェミニズムの中には、建設的な議論を拒否し、一方的に攻撃するケースも少なくありません。
例
- SNS上での誹謗中傷
- 企業広告やアニメに対する過激な批判(例:「女性キャラクターが性的すぎる」など)
参考
SNS上での「炎上型フェミニズム」は、一般の人々がフェミニズムそのものに悪い印象を抱く要因になっていると指摘されています。(出典:PRESIDENT Online)
3. 本来のフェミニズム運動の妨げになる
行き過ぎたフェミニズムが目立つことで、本来のフェミニズム運動が誤解され、賛同者を失うケースもあります。実際、フェミニズムに否定的な意見を持つ人の中には、「フェミニスト=過激な思想を持つ人々」という印象を持っている人も少なくありません。
例
- 「フェミニズムは男性を敵視する運動」と誤解される
- 本来の男女平等を目指す活動が敬遠される
参考
朝日新聞の調査では、日本の若者の中には「フェミニズム=過激なもの」と認識している層が一定数いることが明らかになっています。(出典:Asahi.com)
Z世代のリアルな意見
「なんでこんなにSNSでは頻繁にフェミニズムで対立は起きるのだろう」
「過去に女性が不当に扱われてきた歴史があるからだと思う。今も性差別がゼロになったわけじゃないし、怒りが爆発してる人もいるのかも。」
「そうそう。それに、SNSは短い言葉で注目を集めるから、過激な発言のほうが拡散されやすいっていうのもあるね。」
「でも、それって逆効果じゃない? 俺みたいに“フェミニズムって怖いな”って思う人も増えてるんじゃ?」
「そこが問題なんだよね。行き過ぎたフェミニズムのせいで、本当に必要な男女平等の議論が進まなくなってる。」
「知って欲しいのは、フェミニズムの本来の意図は“男性批判”ではなく、“社会の不平等をなくす運動”この根本を共有することが大事だと思う。」
この対話を読んで、あなたはどう感じましたか?
フェミニズムの本来の意義を再考する
ここまで「行き過ぎたフェミ」の問題点を見てきましたが、それでは本来のフェミニズムの意義とは何でしょうか?
1. 男女ともに平等な社会の実現
フェミニズムは、単に女性の権利を拡大するだけでなく、男性の生きづらさも含めて解決を目指すものです。例えば、日本では男性の育児休業取得率の低さが問題になっています。これも、ジェンダーによる役割分担の固定観念が影響しており、フェミニズムが関与すべき課題の一つです。
参考:
厚生労働省のデータによると、日本の男性の育休取得率は2022年時点で約14%と、依然として低い水準にあります。
2. 対話を重視するフェミニズムの重要性
建設的な対話を通じて、男女平等を推進することが必要です。SNSでは過激な主張が目立ちますが、実際には穏健派のフェミニストも多く、社会をより良くするために活動を続けています。
まとめ
「行き過ぎたフェミ」と言われる現象がある一方で、フェミニズムの本来の意義は決して否定されるべきものではありません。男女平等を実現するためには、極端な言動ではなく、対話と理解が重要です。フェミニズムに関する議論をより建設的なものにしていくために、私たち一人ひとりが冷静な視点を持ち、バランスの取れた議論を行うことが求められています。
こちらもおすすめ