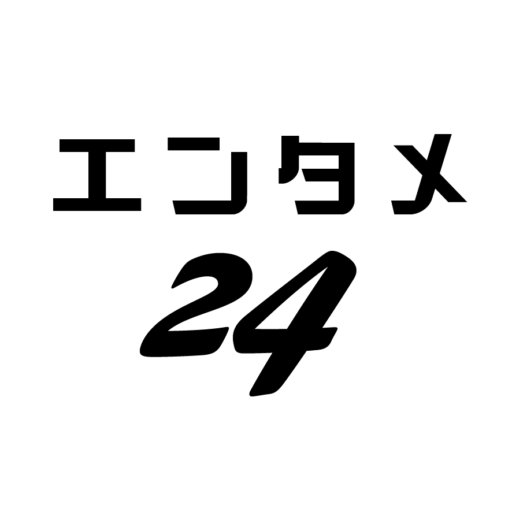“The Big Short”の男、再び市場に警鐘
2008年のリーマン・ショックを予言した伝説の投資家、マイケル・バリー(Michael Burry)氏。
彼は映画『マネー・ショート(The Big Short)』のモデルとして知られ、危機をいち早く察知した人物として世界的に有名です。
そんな彼が今、AIブームに沸くテック業界に対して新たな警告を発しています。
映画『マネー・ショート』とは?
『マネー・ショート』は、リーマン・ショックの引き金となった住宅ローン市場の崩壊を題材にした実話ベースの映画です。
クリスチャン・ベールが演じるバリー氏は、誰も信じなかった「住宅バブル崩壊」を予測し、逆張りの投資(空売り)で巨額の利益を手にします。
この作品は、金融業界の「集団盲信」や「数字への過信」を痛烈に批判し、経済を学ぶ上での教科書のような存在になっています。
そして今、バリー氏は再び“常識を疑え”と警鐘を鳴らしているのです。
今回の標的は「AIバブル」と“会計トリック”
バリー氏によれば、AIブームを支える大手テック企業が利益を実際より多く見せている可能性があるとのこと。
その理由が、「減価償却の見積もり」です。
「テクノロジーが急速に進化しているのに、企業は設備の寿命を不自然に長く設定している」
──マイケル・バリー
減価償却とは何か?
企業が機械やサーバーなどを購入すると、その資産は時間とともに価値が減るため、会計上は「減価償却費」として少しずつ費用に計上します。
例えば10億円のAIサーバーを買った場合、
- 「5年使う」とすれば、毎年2億円が費用になる。
- 「10年使う」とすれば、毎年1億円しか費用にならない。
つまり、耐用年数を長く設定すればするほど、当期の利益が増えるというわけです。
バリー氏はこの“見えにくい操作”を、「現代版の利益粉飾」だと批判しています。
「AI時代に寿命を延ばすのは逆行している」
バリー氏が問題視しているのは、クラウドやAIを支えるハードウェア更新のスピードです。
NvidiaのGPUなど、AI関連機器は技術進化が非常に早く、数年で旧型化します。
それにもかかわらず、企業は設備を「6年〜8年使える」としている。
結果として、減価償却費が過少に計上され、利益が膨らんで見えるという構図です。
驚くべき試算──「20兆円規模の利益水増し」?
バリー氏の分析によると、
- 2026〜2028年の3年間で、**約1,760億ドル(約20兆円)**分の減価償却費が過少計上されている可能性がある。
- Oracle(オラクル)は利益を約27%、Meta(メタ)は**約21%**上乗せしている恐れがある。
彼はこの現象を「AIバブルを支える見えない粉飾」と表現し、11月25日に詳細な分析レポートを公表予定としています。
会計の“合法的グレーゾーン”が生むリスク
ここで押さえておきたいのは、これが違法な粉飾ではないということです。
企業は既存の会計ルール(GAAPやIFRS)に従って処理しています。
しかし、問題は「そのルールが現実に合っているか」です。
技術革新が速いAI業界では、会計上の耐用年数が実態を反映していない可能性が高いのです。
つまり、バリー氏の指摘は「法的な粉飾」ではなく、「経済的な粉飾=実態との乖離」への警告だと言えます。
3つの視点
このニュースは投資家だけでなく、社会人や学生にも多くの示唆を与えます。
- 数字の裏側を読む力
決算の「利益」には仮定や前提があり、表面的な数字だけでは実態が見えない。 - 技術と会計のズレ
テクノロジーの進化スピードが、既存の会計ルールを追い越しつつある。 - “常識を疑う”姿勢
『マネー・ショート』の時代と同じく、バブルの兆候は静かに広がる。気づくのは「少数派」だけだ。
まとめ:静かに膨らむ“AIバブル”の影
マイケル・バリー氏の最新の警告は、AI時代の“会計バブル”への注意喚起です。
利益の数字が眩しい企業ほど、その裏にある減価償却の前提を見直す必要があるでしょう。
AIが生み出す利益の輝きの裏で、“見えない粉飾”が静かに進行しているかもしれません。
映画『マネー・ショート』の教訓は、いま再び私たちに問われています。