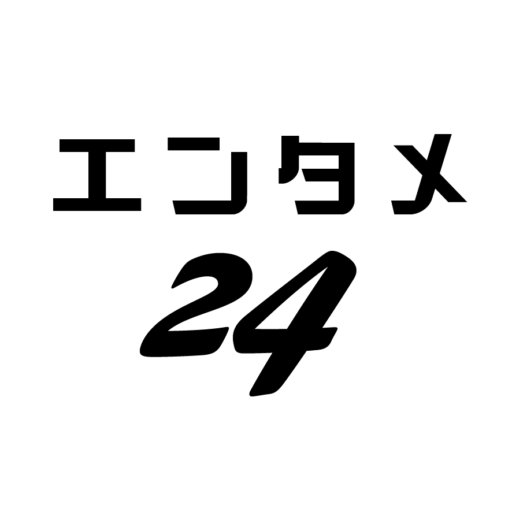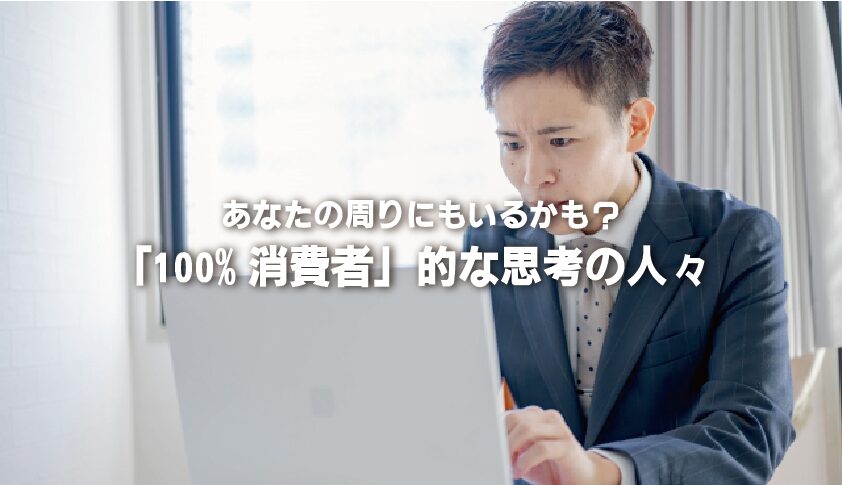あなたの周りにもいる?「100%消費者」的な思考の人々
「週休2日、9-17時勤務」という言葉を聞くと、なんだか理想的な生活が浮かびませんか?日曜は家族とゆっくり過ごし、平日の夕方にはジムや趣味の時間もある。確かに、それは多くの人が憧れる「安定した生活」の象徴です。
でも、ふと思うんです。この枠組みの中に収まることで、消費者思考が高くなることになりやすいんじゃないかって。消費者というのは、ただ買い物をして楽しむ人のことだけじゃなくて、「与えられたものを疑問なく享受する人」のことを指しています。自分で考えたり創り出したりするというより、「与えられたものの中で快適に過ごす」ことに重点が置かれる。これ、便利で快適なんだけど、ちょっと怖くないですか?

あなたの身近に存在している「自己愛人間」。
彼らの7つの大罪とは―。
恥を知らない、歪曲して、幻想をつくり出す、傲慢な態度で見下す、ねたみの対象をこきおろす、特別扱いを求める、他者を平気で利用する、相手を自分の一部とみなす。
他者を犠牲にして自己を守ろうとする自己愛人間の複雑な心理構造を解き明かし、その毒から身を守るための4つの戦略を紹介。
『消費者思考』の感覚とは何か
たとえば、何かトラブルが起きたとします。仕事で問題が発生したり、家庭で不和が起きたりした時に、真っ先に頭に浮かぶのが「なんでこんなことが起きたんだ?自分は何も悪くないのに」という感覚。これは、どこか「自分はただの利用者で、問題を解決する責任は誰か別の人にある」と考える姿勢に似ています。
実際、社会的な安定した枠組みの中で生活していると、この「消費者思考」に陥りやすい。会社では決まった時間に仕事を終え、決まった給料をもらい、決まった休日を過ごす。その結果、自分の意志や判断を深く考える機会が減り、責任や選択から逃げたくなる。
この感覚、私も何度も経験してきました。若い頃、バイト先で「お客様は神様」と言われて、なんだか腑に落ちない気持ちになったのを覚えています。「いや、なんで『神』扱いしなきゃいけないんだ?」と。一方で、自分がサービスを受ける側で問題が起こると、急に態度がでかくなる自分もいて、なんだか恥ずかしくなったことも。
消費者思考から生産者思考へ:視点を変えると人生が変わる
「100%消費者」の考え方は、決して悪いわけではありません。誰だって安定した生活を求めるし、便利な社会の恩恵を受けたいと思う。でも、それだけだとどこか味気なく、そして自分の人生に責任を持つ感覚を失いやすい。
そんな時に役立つのが、「生産者思考」を意識することです。つまり、自分が社会や周囲に何を提供できるのかを考える視点です。小さなことでもいいんです。たとえば、友人に新しい趣味を提案してみるとか、職場で誰かが困っていたら手を差し伸べるとか。
生産者思考のいいところは、ただ「与えられる」だけの受動的な状態から脱却できること。たとえば、私がエッセイを書く時、自分の経験をどう伝えれば読者の心に響くかを考える。そのプロセスで、自分の中にあったぼんやりした思いが形になるし、それを読んだ誰かが「共感した」と言ってくれると、自分の存在意義を感じるんです。
自分の中の『イヤさ』と向き合う
でも正直な話、自分の中にも「100%消費者」的な部分がまだあるんですよね。例えば、疲れている時に「なんでこんなに頑張らなきゃいけないんだ?」と思うこともあるし、便利なサービスがなかったらイライラすることもある。だけど、それに気づけた時が大事なんだと思います。
この「イヤさ」に向き合うと、意外と自分を客観視できる瞬間が増えます。「ああ、今自分、他人のせいにしようとしてたな」とか、「ちょっと人任せになってるな」とか。それに気づいたら、少しずつでも自分で責任を取る選択肢を増やせばいい。
結論:与えられるだけじゃつまらない、自分を動かそう
週休2日、9-17時勤務という安定した生活を送る中でも、僕たちには選択肢があります。それは、「100%消費者」として生きるのか、それとも「自分の意志を持って生産者として動く」のかということ。
もちろん、全員が何か大きなことを成し遂げなきゃいけないわけじゃない。でも、自分で選び、考え、行動することで得られる達成感や喜びは、与えられるだけの生活では味わえないものです。
だからこそ、少しだけ視点を変えてみてほしい。たとえば、毎日の通勤途中で見た景色に興味を持つとか、休日に何か新しいことを始めてみるとか。その小さな一歩が、実は大きな変化を生むきっかけになるはずです。
最後に。
私もまだまだ消費者的な部分が多い人間です。でも、そのイヤさに気づきながらも、少しずつ変わろうとする。そのプロセス自体が、人生の楽しさじゃないかと思います。
こちらもおすすめ