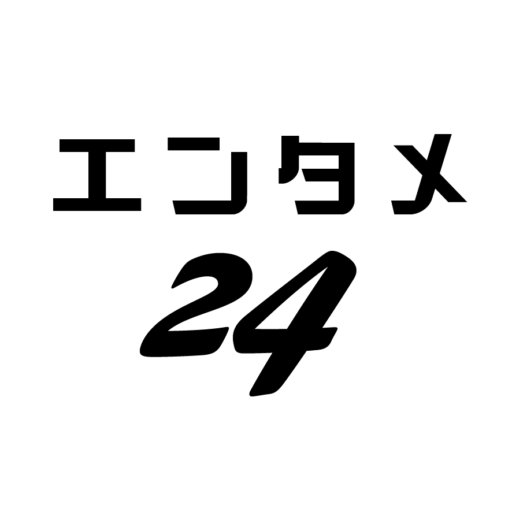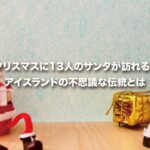チンパンジーもつれションする
つれションの謎:京大の研究成果から考える
日常生活の中で、私たちはふとした瞬間に誰かの行動につられることがある。たとえば、隣の人がスマホを手に取れば自分も確認したくなるし、誰かが大きなあくびをすれば自然とあくびが出ることもある。この「つられる」感覚が動物にも共通していると聞けば、なんだか親近感を覚えるだろう。
2023年、京都大学の研究チームが、チンパンジーにも「つれション」という現象があることを発見した。この現象は、1匹のチンパンジーが小便を始めると、近くの個体がつられるようにして小便をする確率が高いことを示している。また、地位の低い個体ほどその傾向が強いというのだ。ここには、私たちが日々の生活で感じる「他人に影響される自分」と通じる何かが隠されているように思う。

今日話題のふるさと納税はこれ
なぜ「つられる」のか:心理的メカニズムを探る
チンパンジーのつれションを知ると、人間の心理的な「つられ行動」との共通点を考えずにはいられない。心理学では「ミラーニューロン」という言葉がよく使われる。これは、他者の行動を観察したとき、自分の脳内でも同様の神経活動が起こる仕組みのことだ。たとえば、誰かが笑うとこちらも笑顔になりやすいし、悲しむ人を見れば心が痛む。この共感の基盤となるミラーニューロンの働きが、チンパンジーのつれションにも関係しているのではないだろうか。
さらに興味深いのは、「地位の低い個体ほどつられやすい」という点だ。これを人間社会に置き換えると、組織やコミュニティで目立たない人ほど、周囲の影響を受けやすいという現象に似ている。これは、自己防衛や集団への適応の一環として、他者の行動をコピーすることで安心感を得る心理的な働きが関与している可能性がある。
人間社会における「つられ」の功罪
ここで、私たちの身近な「つられ行動」に目を向けてみよう。例えば、SNSで流行しているトレンドに乗っかったり、街中で行列を見かけて「美味しいに違いない」と並んでしまったり。これらは誰もが経験する「つられ」の一例だ。
しかし、つられる行動にはメリットとデメリットがある。メリットとしては、新しいことを試すきっかけになったり、集団に溶け込みやすくなったりする点が挙げられる。一方で、流されるばかりでは自己を見失い、結果的に後悔を招くこともある。たとえば、友人が買った商品をなんとなく真似して購入したけれど、後から「あまり必要なかったな」と気づく瞬間。
このように、「つられ」は私たちの生活において重要な役割を果たしつつも、使いどころを間違えれば厄介な存在になることを示している。
チンパンジーからの学び
チンパンジーのつれションをきっかけに考えると、私たち人間ももっと「自分らしさ」について意識を向けるべきだと気づかされる。他人の影響を受けるのは自然なことだが、その影響をどのように活用するかがカギになる。
たとえば、地位が低い個体ほどつられやすいという研究結果は、他者の行動に流されやすい自分を責めるのではなく、むしろそれを自己成長の材料にするという考え方を提案してくれる。つられることで得られる安心感や情報を活用しつつ、自分が本当に大切だと思うことを見極める力を鍛えていく。そのバランスが取れれば、「つられ」は恐れるべきものではなくなる。
つられた先にある新しい景色
京大の研究チームが明らかにしたチンパンジーのつれションは、ただの面白い現象として片付けるにはもったいないほど、人間社会にも通じる深い示唆を与えてくれる。私たちが日々感じる「つられ」の感覚は、時に厄介なものに思えるけれど、それ自体が成長や発見のきっかけになる可能性を秘めている。
次回、誰かの行動につられている自分に気づいたら、それを単なる反射的な行動と捉えるのではなく、「自分はここから何を得られるだろう?」と考えてみてほしい。その小さな問いかけが、新しい景色への扉を開く第一歩になるかもしれない。チンパンジーのつれションから見えてくるのは、他者と影響し合いながら生きる私たちの「らしさ」そのものなのだ。
こちらもおすすめ