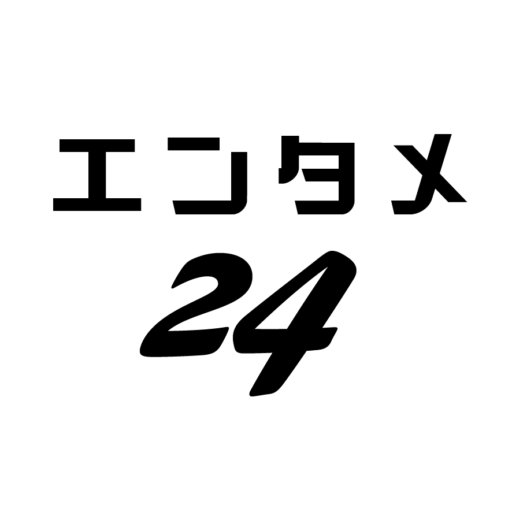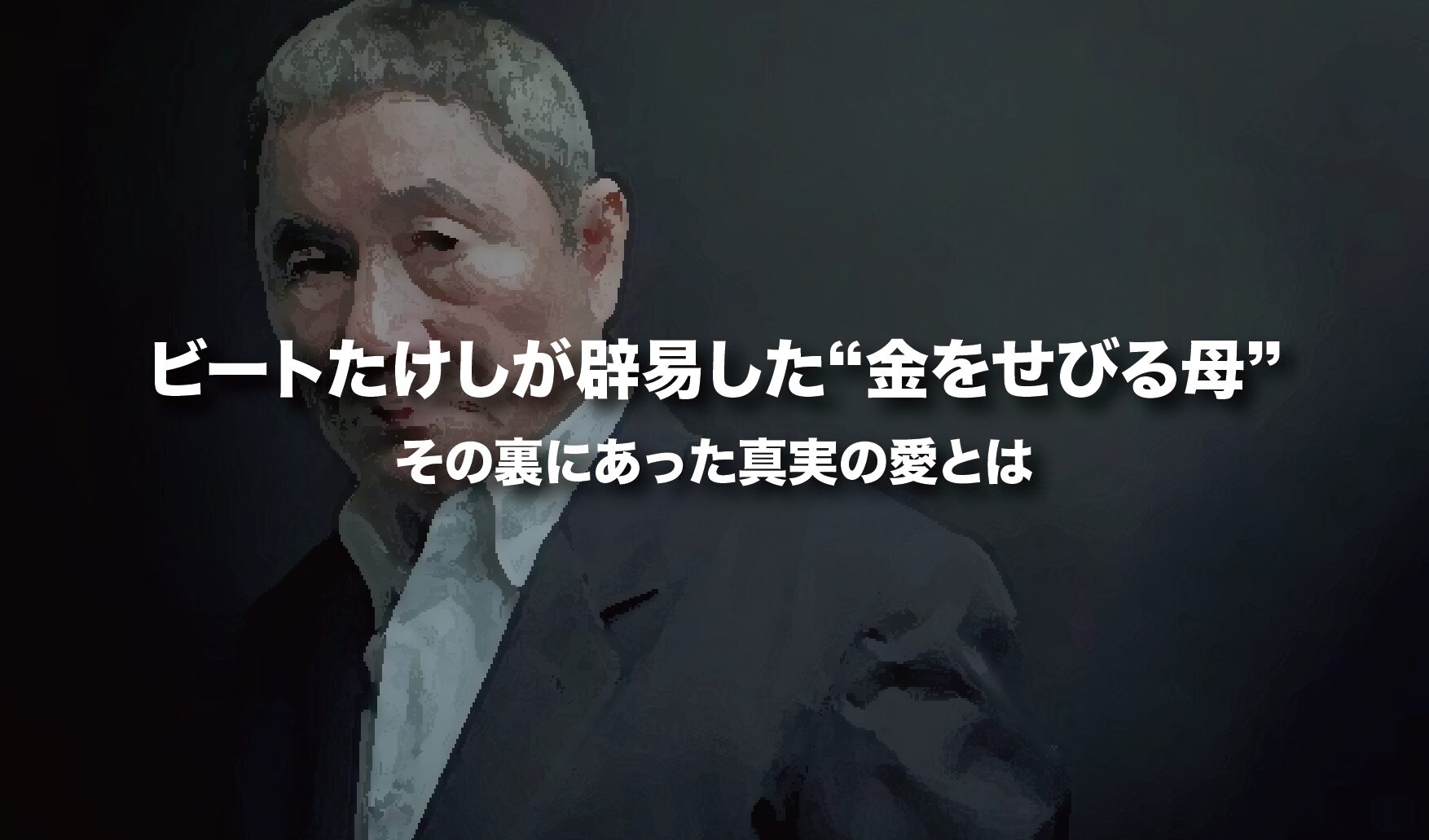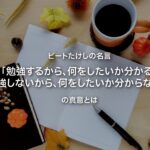ビートたけしが辟易した“金をせびる母”から学ぶ

まえがき
第一章 このおかしな世の中はどうできているのか
みんな、ニワトリ小屋のニワトリだよ/ひとりでも生きていけるのに/人工知能に支配される集団/0と1みたいに単純化したらつまらない/楽に生きられるというシステムの罠/「常識を疑う」ことの大切さ/シンギュラリティは起きない/もし量子コンピュータが実用化されたら/金儲けに狂奔する人間/人間の愚かな勘違い/このままだと人間は絶滅するんだろうね/摩訶不思議な日本経済の仕組み/細かく序列を設けていく金持ちのやり方/貧乏な人を絡め取るシステム/上品と下品について/変化する「武士は食わねど高楊枝」の意味
1. お金って、なんだろう?
お金は怖い。
あったらあったで揉めるし、なかったらなかったで揉める。貯めたところで価値は変動するし、使ったところで満足が続くわけでもない。でも、お金がないと、選択肢すら持てないことがある。
そんなことを思いながら、僕はこの話を思い出した。
ビートたけしが売れてから、母親がやたらとお金をせびるようになった話だ。
芸人として大成功を収め、大金を稼ぎ始めた彼に、母親はひたすら「金をよこせ」と言い続けた。たけしは、内心辟易しながらも、言われるがままに大金を渡し続けた。
しかし、後に大事故に遭い、顔面麻痺の大けがを負って入院したとき、彼の母親は通帳を持って病室を訪れる。そして、「この金で暮らせ」と、今まで受け取った金がすべてそのまま口座に残っていることを見せたのだ。
母親は、息子がいつ仕事を失っても生きていけるようにと、強制的に稼ぎを徴収し、備えていたのだった。
これを聞いたとき、僕は「すごいな」と思った。親って、表向きは小言ばっかり言ってるけど、実は見えないところで子どもの人生を支える覚悟を決めているものなのかもしれない。
2. 「なんで俺の金を?」とムカつく気持ち
たけしが母親に金を渡していた頃、きっと「なんで俺が稼いだ金を、母親に渡さなきゃならないんだ?」という気持ちはあったはずだ。
これ、たぶん多くの人が経験したことがある感情だと思う。
例えば、社会人になって初めての給料をもらったとき、「親に何か買ってあげようかな」と思いつつ、「いや、でもせっかく稼いだお金なんだから、自分のために使いたい」という気持ちも湧く。
また、実家暮らしをしている人が「家に金を入れろ」と親に言われると、「いやいや、生活費はそっちの役目でしょ」と反発したくなることもある。
お金って、稼いだ人間のものだという感覚がある。でも、たけしの母親の行動は、その考え方をひっくり返す。彼女は、「今、息子に自由にお金を使わせること」よりも、「未来に困らないようにすること」を優先したのだ。
3. 人はいつか転ぶ、そのときに
「自分の力でなんとかする」というのは、かっこいい考え方だ。でも、本当にどうにもならなくなることは、人生には普通にある。
たけしは大事故に遭った。売れっ子の芸人として、どんなに稼いでいても、あの事故がキャリアを終わらせる可能性は十分にあった。
このとき、母親が「これで暮らせ」と差し出した通帳は、ただの紙切れではなかったと思う。そこには、「お前が倒れることも考えていたよ」という親の覚悟が詰まっていた。
人間は、どんなに順調でも、ある日突然転ぶことがある。それは病気かもしれないし、失業かもしれない。信用していた人に裏切られることもあるし、思ってもいなかった形で孤独になることもある。
そんなとき、「転んだ先にちゃんと地面がある」ことが、どれほど心強いか。たけしの母親は、それを用意していたのだ。
4. 「渡す」と「奪われる」は違う
ここで誤解してはいけないのは、「親に金をむしり取られることが正しい」という話ではないことだ。
大人になれば、親の言うことが正しいとは限らないと気づく瞬間もある。親子といえども、人間同士だから、価値観が合わないこともあるし、時には傷つけ合うこともある。
ただ、「誰かにお金を渡すこと」は、必ずしも搾取ではないということだ。
たけしの母親は、息子から金を受け取るとき、きっと何も説明しなかっただろう。だからこそ、たけしは「なんでこんなに金をせびるんだよ」と思っていたはずだ。
でも、母親はただの浪費家ではなかった。「いつか必要になるときのために」と思いながら、静かに貯め続けた。
この話は、お金の本質を考えさせられる。誰かにお金を「渡す」ことが、ただの「奪われる」ことではない場合もある。大事なのは、その使い道に意味があるかどうかだ。
5. 「見えないところで支えられている」
たけしの母親の話を聞いて思うのは、「見えないところで誰かが支えてくれていること」に気づくのは、往々にして遅れるということだ。
僕たちは、自分が頑張っていることにばかり目が行く。でも、その頑張りを陰で支えてくれる人がいることには、なかなか気づかない。
それは親かもしれないし、友達かもしれないし、同僚かもしれない。支えてくれる人は、たいてい何も言わない。でも、ある日ふとした拍子に気づく。「ああ、あのとき、あの人がいたから俺はここにいられるんだ」と。
そして、それに気づいたときには、もうその人は目の前にいないことが多い。たけしが母親の葬式で号泣したのは、そんな「遅れた気づき」が胸を突いたからかもしれない。
6. 未来の自分のために、誰かのために
この話を聞いて、「自分の大切な人が困ったときに、自分は何ができるだろう」と考えた。
お金だけじゃない。時間でも、言葉でも、ただそばにいることでもいい。
誰かが転びそうになったとき、何かしらの「地面」になれる準備をしておくこと。それは、回り回って、自分が転んだときの支えにもなる。
たけしの母親は、息子に「備えることの大切さ」を教えてくれた。
僕たちも、いつか誰かのために、見えないところで支えられる存在になれるだろうか。
ふと、そんなことを考えた。
こちらもおすすめ