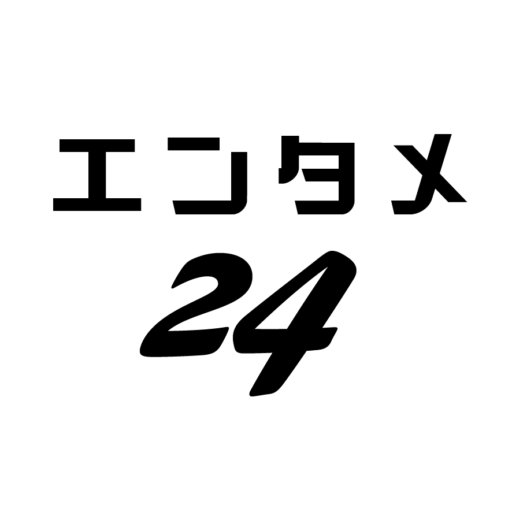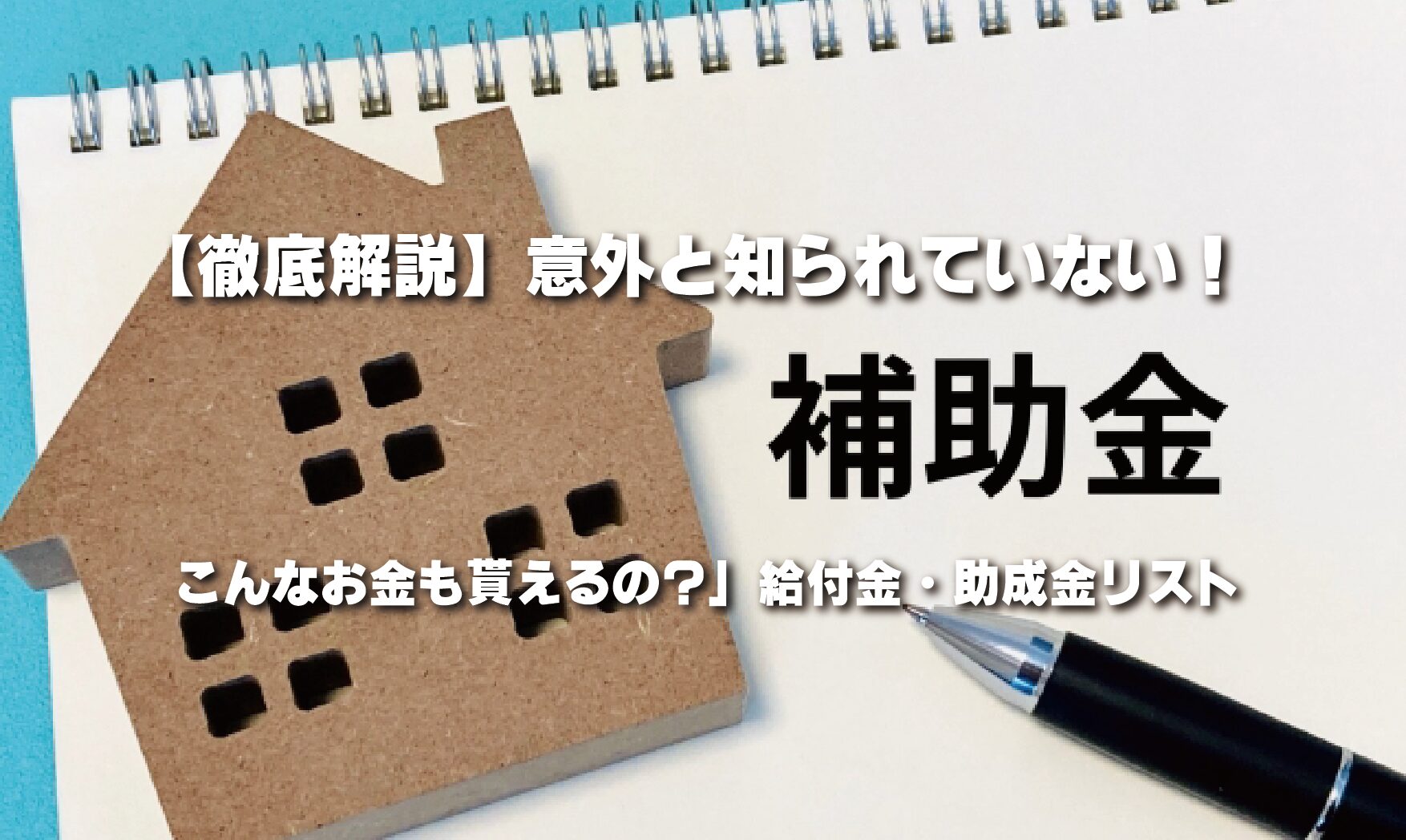貰えるお金をフル活用して賢く生活する方法
物価の上昇が続く中、利用可能な給付金や補助金を活用することは、家計の負担を軽減する有効な手段です。以下に、さまざまな状況で申請可能な支援金について、具体的な金額や条件を交えてご紹介します。

ニューヨークタイムズのNo.1ベストセラー。全世界で1500万部突破!
日々の小さな変更が、驚異の結果をもたらす。
本書は学術研究論文ではなく、実践マニュアルである。著述はすべて科学的に裏付けられ、過去の最高のアイデアと科学者たちによる説得力のある発見を統合したものだ。参考にしている分野は、生物学、神経科学、哲学、心理学などだ。特に重要なアイデアを見いだし、すぐ実行できる形で結びつけることで役に立つ構成になっている。
その根幹をなすものは、習慣の4つのステップ――きっかけ、欲求、反応、報酬――と、このステップから生まれる4つの行動変化の法則である。わたしが提案する枠組みは、認知科学と行動科学の統合モデルである。
再就職支援:最大50万円
再就職を目指す方には、職業訓練受講給付金や教育訓練給付金などの支援制度があります。これらの制度を活用することで、再就職活動やスキルアップに必要な費用を補助してもらうことが可能です。
職業訓練受講給付金
雇用保険の受給資格がない方が公共職業訓練を受講する際、一定の条件を満たすことで、月額10万円の給付金を最長6ヶ月間受け取ることができます。これにより、最大60万円の支援を受けることが可能です。
教育訓練給付金
雇用保険の被保険者期間が一定以上ある方が対象で、指定の教育訓練を受講し修了した場合、支払った費用の一部(上限あり)が支給されます。一般教育訓練給付では上限20万円、専門実践教育訓練給付では上限50万円の支給が受けられます。
これらの制度を活用することで、再就職やキャリアチェンジに伴う経済的負担を軽減できます。詳細な条件や申請手続きについては、厚生労働省の公式サイトや最寄りのハローワークで確認してください。
家賃滞納支援:最大7万円
家賃の支払いが困難な場合、住居確保給付金を利用できる可能性があります。この制度は、離職や休業等により経済的に困窮し、住居を失う恐れがある方を対象に、家賃相当額を一定期間支給するものです。
住居確保給付金
支給額は地域や世帯の状況によって異なりますが、例えば東京都の場合、単身世帯で月額53,700円、2人世帯で64,000円、3人世帯で69,800円が上限となっています。支給期間は原則3ヶ月ですが、条件を満たせば最長9ヶ月まで延長可能です。
家賃滞納が続くと、住居を失うリスクが高まります。早めに自治体の窓口や生活困窮者自立支援機関に相談し、適切な支援を受けることが重要です。
墓じまい支援:最大70万円
近年、少子高齢化や核家族化の進行に伴い、墓じまいを検討する方が増えています。墓じまいには費用がかかりますが、一部の自治体では、その費用を補助する制度を設けている場合があります。
墓じまい費用の補助
例えば、ある自治体では、墓じまいにかかる費用の一部を補助する制度を設けており、上限額は50万円となっています。また、別の自治体では、墓じまい後の改葬先として共同墓地を利用する場合、その費用を含めて最大70万円の補助を行っています。
補助の内容や条件は自治体によって異なりますので、墓じまいを検討されている方は、まずお住まいの自治体に問い合わせてみることをお勧めします。
スキルアップ支援:最大10万円
スキルアップを目指す方には、各種の支援制度があります。特に、教育訓練給付金制度は、一定の条件を満たすことで、受講費用の一部が支給されます。
一般教育訓練給付金
雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は1年以上)ある方が対象で、指定の教育訓練を受講し修了した場合、支払った費用の20%(上限10万円)が支給されます。
この制度を活用することで、自己負担を軽減しながらスキルアップを図ることができます。詳細な条件や対象となる講座については、厚生労働省の公式サイトや最寄りのハローワークで確認してください。
偏頭痛治療薬費用支援:年間最大9万円
慢性的な偏頭痛に悩まされている方にとって、医療費の負担は大きなものです。しかし、高額療養費制度を利用することで、一定額以上の医療費が戻ってくる可能性があります。
高額療養費制度
この制度では、1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。自己負担限度額は所得や年齢によって異なりますが、例えば年収370万円〜770万円の方の場合、月額約90,000円が上限となります。
偏頭痛の治療でロキソニンなどの薬を継続的に使用している場合、年間の医療費が高額になることがあります
インフルエンザ予防接種の補助:最大2,000円
インフルエンザの予防接種は、特に冬場に感染リスクを下げるために重要ですが、費用がかかります。しかし、一部の自治体では補助制度を設けており、無料または一定額の助成を受けることが可能です。
自治体ごとの助成金額
- 高齢者(65歳以上)や基礎疾患を持つ人
多くの自治体では、65歳以上の高齢者や基礎疾患を持つ方を対象に、インフルエンザ予防接種の助成を行っています。助成額は地域によって異なりますが、1,000円~2,000円程度が一般的です。 - 妊婦・子ども(生後6ヶ月~小学生)
一部の自治体では、妊婦や子どもに対しても助成が行われています。例えば、東京都の一部自治体では、小学生以下の子どもには2,000円の補助が出るところもあります。
申請方法
助成を受けるためには、自治体の指定医療機関で接種を受ける必要があります。事前に自治体のホームページで確認し、必要な書類(健康保険証や接種券)を用意しましょう。
高齢者向けiPhone購入補助:最大3万円
高齢者のデジタルデバイド(情報格差)を解消するため、一部の自治体ではスマートフォン購入の補助制度を実施しています。特に、デジタル行政サービスの利用促進を目的とした支援が増えています。
補助金の内容
- 対象者:65歳以上の高齢者
- 補助額:最大3万円
- 目的:スマホを活用した健康管理、行政サービス利用の促進
例えば、神奈川県のある自治体では、スマホ購入時に最大3万円の補助を行っています。また、スマホの基本的な使い方を学べる無料講習会も実施されています。
申請手続き
申請には、自治体指定の販売店でスマホを購入し、領収書とともに申請書を提出する必要があります。詳しくは自治体の広報やホームページを確認しましょう。
資格取得後の就職支援:最大56万円
新たな資格を取得し、就職を目指す方には、求職者支援制度や教育訓練給付金制度が活用できます。
求職者支援制度(最大月10万円 × 6ヶ月)
雇用保険を受給できない方が、職業訓練を受けながら生活支援を受けられる制度です。
- 対象者:ハローワークで求職活動を行っている人
- 支給額:月10万円(6ヶ月間で最大60万円)
教育訓練給付金(上限56万円)
資格取得のための費用の一部を国が補助する制度で、以下のような種類があります。
- 専門実践教育訓練給付:資格取得後の就職が条件。受講費用の最大70%(上限56万円)が支給される。
- 一般教育訓練給付:受講費用の20%(上限10万円)が支給される。
特に、IT関連、介護、医療事務などの資格が人気です。
iPhoneを盗まれた場合の補償:最大5万円
スマホの盗難に遭った場合、補償を受けられる制度があります。
補償を受ける方法
- 携帯キャリアの補償サービス
- docomo、au、SoftBankでは、月額500円~800円のオプションに加入していれば、端末の再購入費用の一部が補償される。
- AppleCare+(iPhone向け補償)に加入していれば、盗難・紛失時に最大5万円の補償が適用される。
- クレジットカードの補償
- 一部のクレジットカードでは、購入から一定期間内の盗難・破損を補償するサービスがある(例:ゴールドカード以上)。
- 警察への被害届提出
- 盗難届を出すことで、保険や補償の適用がスムーズになる。
仕事を辞めた場合の失業給付:最大24万円
仕事を辞めた場合、**失業保険(基本手当)**を受け取ることができます。
失業保険の計算方法
失業手当は、**退職前の給与の50~80%**が支給されます。例えば、
- 月収30万円 → 1日あたり6,000円支給(1ヶ月で約18万円)
- 月収20万円 → 1日あたり4,500円支給(1ヶ月で約13.5万円)
失業手当は90日~330日受給できるため、最大で100万円以上の支援を受けることが可能です。
申請手続き
ハローワークで求職活動を行い、一定の条件を満たすと支給されます。早めに手続きを進めましょう。
テスラ購入補助:最大65万円
電気自動車(EV)の購入には、国や自治体から補助金が出ます。
国の補助金制度
- CEV補助金(経済産業省):最大85万円
- 自治体の補助金:最大50万円(東京都の場合)
例えば、テスラ・モデル3の購入時に、国から最大65万円、自治体からの補助を合わせるとさらに割引を受けることが可能です。
申請方法
- 車の購入後、自治体や経済産業省のサイトから申請
- 申請には、納車証明書や車検証のコピーが必要
EV購入を検討している方は、補助金を活用することで数十万円の節約が可能になります。
免許返納での支援:最大3万円
高齢者の運転免許返納を促進するため、多くの自治体で補助金制度を実施しています。
補助金の内容
- バス・タクシー券の配布(1万円~3万円分)
- 電子マネーや商品券の支給(一部自治体)
例えば、東京都では免許返納後に最大3万円相当のタクシーチケットが支給される制度があります。
申請方法
免許センターや警察署で手続きを行い、交付証明書を持って自治体に申請します。
まとめ
申請すれば受け取れるお金は意外と多く存在します。
- 再就職支援(50万円)
- 家賃滞納支援(7万円)
- 墓じまい補助(70万円)
- スキルアップ支援(10万円)
- 高額療養費制度(9万円)
- インフルエンザ予防接種助成(2,000円)
- 高齢者向けiPhone購入補助(3万円)
- iPhone盗難補償(5万円)
- 失業給付(24万円)
- EV購入補助(65万円)
- 免許返納補助(3万円)
今すぐ申請できる制度も多いため、貰えるお金はしっかり活用しましょう!
こちらもおすすめ