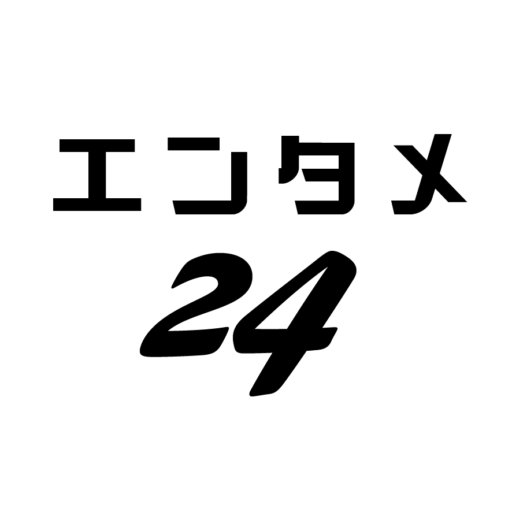藤田晋が語る、Z世代を本気にさせる意外な方法とは?
1. はじめに
現代の若者、特にZ世代は、従来の世代とは異なる価値観を持っている。サイバーエージェントの藤田晋氏が語るように、彼らを本気にさせ、自走させるためには「稼げる環境」を作ることよりも、「未達することのカッコ悪さ」や「周囲からの冷たい反応」を意識させることが効果的だという。この記事では、Z世代の特徴とその動機づけのメカニズムを探りながら、どのように彼らを自走させることができるのかを考察する。

ベストセラー『渋谷ではたらく社長の告白』から8年。
ネットバブル崩壊、業界の低迷、再びのネットバブル。
絶頂の中、発生したライブドア事件、親友・堀江氏の逮捕、株価暴落、そして社長の退任を賭けて挑んだ未知の領域――。
2. Z世代の特徴と価値観の変化
2.1 Z世代とは?
Z世代とは、1990年代後半から2010年代初頭に生まれた世代を指し、デジタルネイティブとして育った特徴がある。彼らはスマートフォンやSNSとともに成長し、情報を瞬時に取得し、共有することが当たり前の環境にいる。
2.2 欲よりも「恥」や「悲劇感」が行動を促す
過去の世代は「お金を稼ぎたい」「成功したい」という欲求がモチベーションになっていた。しかし、Z世代は「恥をかきたくない」「周囲から否定されたくない」といった感情がより強い。これは、SNSの影響で「自分の評価がリアルタイムで可視化される」環境に生きていることが大きい。彼らにとって、承認されることが何よりも重要であり、それが行動を駆り立てる要因になっている。
3. 「未達することのカッコ悪さ」を活用した動機づけ
3.1 競争環境の作り方
企業や組織において、Z世代が自発的に動く環境を作るには、彼らが「未達することが恥ずかしい」と思う状況を演出することが有効だ。例えば、目標達成を可視化し、未達の人が一目で分かるようなシステムを導入することが考えられる。
具体的な施策例
- ランキング制度の導入:営業成績や成果を社内でランキング化し、定期的に発表する。
- SNS的な評価システム:チームメンバー同士で成果を評価し合う仕組みを取り入れる。
- 小さな成功の積み重ねを促す:短期間で達成可能な目標を設定し、それを逃すと「恥ずかしい」と思わせる。
3.2 周囲の反応を活用する
Z世代は他者からの評価を非常に気にするため、「未達=冷たい反応が返ってくる」という環境を作ることが有効である。
具体的な施策例
- 未達者へのフィードバックの強化:未達者に対して「次はどうするのか?」という建設的な指摘を行い、放置しない。
- チーム単位での評価を取り入れる:個人の達成度だけでなく、チーム全体の目標達成率を重視し、未達成のメンバーがいるとチーム全体に影響が出るようにする。
- ロールモデルの活用:成功者の姿を見せることで、「達成することがカッコいい」という文化を作る。
4. 企業・組織における実践事例
4.1 サイバーエージェントの成功事例
サイバーエージェントは、20代の若手社員を中心にした組織でありながら、圧倒的な成果を出し続けている。その理由の一つが、「未達のカッコ悪さ」を活用した仕組み作りにある。
- ピアプレッシャーを活用したマネジメント
- 「目標達成が当たり前」という文化を作り、未達者が少数派になるようにする。
- 明確な評価基準とフィードバックの徹底
- 成果が可視化され、未達成者が明確にわかる仕組みを採用。
4.2 他企業の取り組み
他の企業でも、Z世代の特徴を活かした仕組み作りが進められている。
- リクルート:目標達成のための「社内SNS」を活用し、未達成者には適切なフィードバックを行う。
- メルカリ:社員同士の評価制度を導入し、「他者からの評価」をモチベーションにする。
5. まとめ:Z世代の本気を引き出すマネジメントのポイント
5.1 「稼ぐ」よりも「未達のカッコ悪さ」
従来のように「報酬」をモチベーションにするのではなく、未達成による心理的なプレッシャーを活用することで、Z世代は自走しやすくなる。
5.2 競争環境と可視化の重要性
競争環境を作り、成果を可視化することで、「未達が恥ずかしい」という感情を刺激する。
5.3 周囲の反応を活用する
「未達成者への冷たい反応」や「フィードバックの徹底」によって、目標達成が当たり前になる環境を作る。
6. 終わりに
Z世代は「欲望」よりも「恥や悲劇感」によって行動を起こす。これを理解し、適切にマネジメントすることで、彼らのポテンシャルを最大限に引き出すことが可能だ。今後の企業経営や組織運営において、この視点を活かした戦略が求められるだろう。
こちらもおすすめ