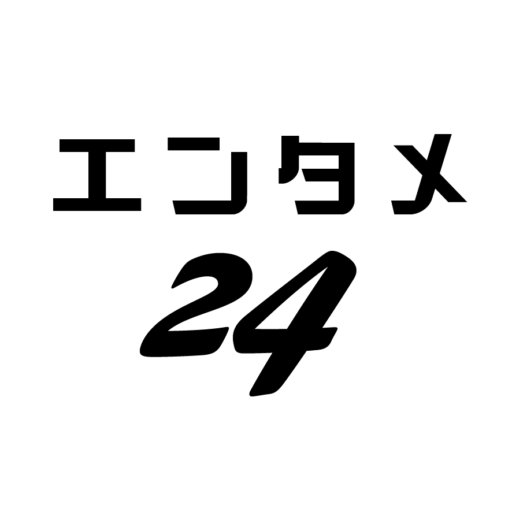『ルックバック』をさらに楽しむための5つの豆知識
映画『ルックバック』は、そのストーリーの力強さと深いテーマ性で観客を強く惹きつけます。けれども、この作品には表面的な物語以上に、細部にちりばめられた仕掛けや背景知識が隠されています。
こうした「豆知識」を知って鑑賞すると、映画の理解が深まるだけでなく、思わずもう一度見返したくなるはずです。
本記事では、藤本タツキが描いた世界をさらに堪能できる5つのトリビアをご紹介します。
『ルックバック』とは
本作は『チェンソーマン』を完結させた鬼才・藤本タツキが発表した143ページの大作読み切りを原作とする映画です。
物語の主人公は、小学4年生で学生新聞に4コマ漫画を連載する藤野。才能を認められつつも、ある日教師から「不登校の生徒・京本の漫画も載せたい」と告げられます。やがて出会った二人の少女は、それぞれの孤独や葛藤を抱えながらも、漫画にすべてを注ぎ、共に成長していくことに。
彼女たちの関係は、人生の選択や偶然の連なりが運命を形作ることを、静かに、しかし強烈に観る者に訴えかけます。
5つのトリビア
1. 部屋に貼ってあるポスター「バタフライ・エフェクト」
映画『ルックバック』のあるシーンで、キャラクターの部屋には「バタフライ・エフェクト」のポスターが貼られています。このポスターは、映画のテーマと深く関連しています。バタフライ・エフェクトとは、些細な行動や出来事が未来に大きな影響を与えるという理論です。このポスターの存在は、映画の中で描かれるキャラクターの選択や行動が、どのようにして未来を変えていくのかを暗示しています。監督はこのポスターを意図的に配置し、視覚的にもそのテーマを強調することで、観客に深いメッセージを伝えようとしています。
2. 所々で出てくるサメ
映画『ルックバック』の中で、様々な場面でサメが登場します。例えば、授業中に先生がサメの絵を描いていたり、キャラクターが水族館でサメを見に行ったりするシーンがあります。これらのサメの登場は、主人公が漫画家として『シャークキック』という作品を描くことへの伏線となっています。サメは映画の中で象徴的な存在として描かれており、主人公の成長や将来の職業選択に影響を与える重要な要素となっています。
3. 京本が美大時代に描いている扉
映画『ルックバック』の中で、京本が美大時代に描いている扉の絵があります。この扉は、藤本タツキの同作品『チェンソーマン』で描かれている「開けてはいけない扉」と非常に似ていることで知られています。『チェンソーマン』の中で「開けてはいけない扉」は重要な象徴であり、未知の恐怖や運命の選択を表しています。『ルックバック』でもこのモチーフを取り入れることで、視覚的な共鳴を生み出し、作品間の深い関連性を感じさせます。
4. インターステラーのオマージュ
映画『ルックバック』の終盤に登場するシーンでは、京本の部屋と彼女の家の廊下を隔てるドアが重要な役割を果たします。このシーンは、クリストファー・ノーランの映画『インターステラー』のオマージュとして知られています。『インターステラー』では、主人公が娘の部屋と家の廊下を隔てる本棚を通じてコミュニケーションを試みます。『ルックバック』でも同様に、ドアがキャラクター間の感情的なつながりを象徴しています。
5. 『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』のジャケットが描かれているシーン
映画『ルックバック』の中には、クエンティン・タランティーノの『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』のジャケットが描かれているシーンがあります。『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』は、アメリカで実際
まとめ
今回は、映画『ルックバック』をより深く味わえる5つのトリビアをご紹介しました。
これらのディテールを踏まえて改めて鑑賞すれば、見過ごしていた仕掛けや、キャラクターたちの選択に込められた意味が立ち上がってくるはずです。
ぜひもう一度スクリーンに向かい、藤本タツキの世界に浸ってみてください。新たな発見が、きっとあなたを待っています。
こちらもおすすめ