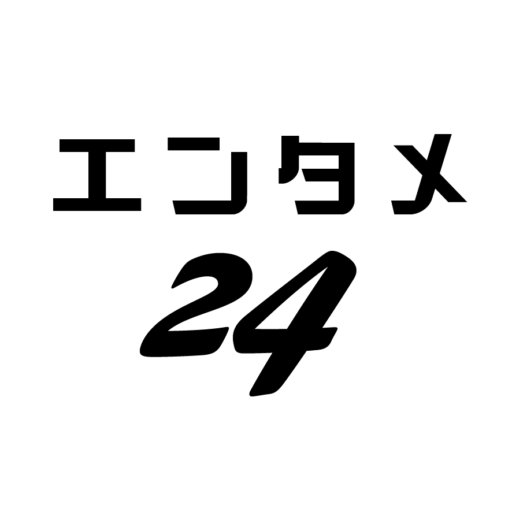「趣味は楽しむものなのに、どうして人はそんなに真剣になるのか。」
SNSでは、「趣味を仕事にすべきか」「下手でも楽しめばいいのか」など、趣味をめぐる議論が絶えません。
映画『ルックバック』を観たとき、その理由の一端が見えた気がしました。
本稿では、藤野と京本という二人の創作を通して、生きづらさから生まれる表現と承認を求めて磨かれる技術のあいだにある“趣味の本質”を考えます。
「ルックバック」とは

ルックバックを見る
趣味に論争が起きる理由とは?
「趣味」という言葉は一見穏やかで、自由な響きを持っています。
しかし現実には、趣味ほど人の価値観がぶつかりやすい領域もありません。
その理由の一つは、趣味が「生き方」そのものと深く結びついているからです。
どんな趣味であれ、時間と労力をかける以上、「なぜ自分はこれをしているのか」という問いがついて回ります。
そしてその問いに対する答えは、人によってまったく異なる。
「癒しのため」「承認のため」「上達のため」「逃避のため」——どれも正しいけれど、同時に互いを否定しやすい。
たとえば「努力して上達したい人」と「気楽に楽しみたい人」では、同じ趣味でも前提が違います。
そこに齟齬が生まれ、「趣味に真剣すぎるのは変」「やるからには上手くなるべきだ」という論争が生まれるのです。
『ルックバック』が映した創作の二つの原動力
藤野と京本。
映画『ルックバック』では、対照的な二人の少女が「漫画を描く」という同じ趣味・創作を通じて出会い、競い合い、そしてすれ違っていきます。
京本:生きづらさから生まれた表現
京本の漫画には、孤独と静けさが滲んでいます。
彼女は社会との接点が少なく、紙の上でしか自分を表現できない。
彼女にとっての創作は、「世界の中で息をするための行為」だった。
このような生きづらさから逃れるための創作は、切実さと痛みを伴います。
しかしその痛みこそが、他者の心を動かす作品を生む源泉になることもある。
自分の弱さを描くことでしか世界とつながれない——そんな創作の形があるのです。
藤野:承認によって育つ表現
一方で藤野は、人に褒められることで成長していきます。
「上手い」「すごい」と言われることが嬉しくて、もっと上手くなりたくて描く。
このような承認を原動力とした創作は、ポジティブで健全にも見えます。
しかし、やがて彼女は京本の才能に触れ、自分の動機を疑い始める。
「私は本当に描きたいから描いているのか。それとも、褒められたいから?」
この問いが、藤野を苦しめ、そして変化させていきます。
生きづらさと承認欲求──二つの軸が交わる場所
京本と藤野の違いは、創作の「出発点」の違いにすぎません。
どちらが優れているわけでもなく、多くの人はこの二つの間を揺れ動きながら創作しているのだと思います。
たとえば、最初は「誰かに認められたくて」始めた趣味が、
いつの間にか「自分の心を保つための時間」になっていたりする。
逆に、孤独から始めた創作が、人に見てもらえることで初めて意味を持つこともある。
創作とは、「生きづらさ」と「承認欲求」という二つの力が交わる場所に生まれる。
だからこそ、趣味や創作には個人の生き方が強く反映され、論争を生むのです。
趣味の本質とは何か
趣味は、社会の中で自分をどう保つかという「生き方の縮図」です。
上達を目指してもいいし、誰にも見せずに続けてもいい。
他人に理解されなくても、その行為に意味を感じる瞬間があれば、それはもう立派な“創作”です。
『ルックバック』のラストシーンで、藤野はもう一度描き始めます。
失われたものを抱えながらも、線を引き続ける。
そこにあるのは、賞賛でも逃避でもなく、「生きるために描く」という衝動。
趣味に正しさを求めすぎる必要はありません。
どんな動機であれ、続けることそのものに価値がある。
それが、『ルックバック』が教えてくれる“趣味の本質”なのではないでしょうか。
まとめ|趣味で論争が起こるのは「生き方」が映るから
- 趣味には「生きづらさ」と「承認欲求」という二つの動機が共存する
- どちらの動機も人間的であり、創作の原動力になる
- 趣味をめぐる論争は、価値観や生き方の違いが反映されるから起こる
- 『ルックバック』はその葛藤を繊細に描いた作品である
だからこそ、趣味に「正解」はない。
ただ、自分がなぜそれを続けるのか、その理由を見つめ続けること——
それが、創作を通して自分と世界をつなぐ唯一の方法なのだと思います。
こちらもおすすめ